
ウィスパーボイスの出し方と練習法をコツとともに解説します。初心者でも安全に習得でき、歌や朗読で魅力的な声を身につけられる方法をご紹介します。
松陰高等学校町田校では、体験イベントや学校見学を開催しています。
記事に関するお問い合わせは以下までご連絡ください。
Tel : 042-816-3061(平日9:00-18:00)
ウィスパーボイスは、息を多めに含みながら声帯を軽く振動させる発声法です。ささやくような優しい響きでありながら、歌声や話し声として明瞭さを保てるのが特徴です。
よく混同される息漏れ声とは異なります。息漏れ声は声帯がほとんど閉じないため息だけが抜けてしまい、音程や響きが曖昧になります。一方、ウィスパーボイスはしっかりとしたピッチ感や響きを残したまま息の成分を多く含むため、表現力豊かな声を出すことができます。
| 発声法 | 声帯の状態 | 息の量 | 音の特徴 |
| ウィスパーボイス | 軽く閉じて振動 | 多め | 優しい・透明感・明瞭さ |
| 息漏れ声 | 開いて閉じない | 非常に多い | 音程が不明瞭・響きにくい |
ウィスパーボイスは聴く人に柔らかく繊細な印象を与え、感情表現の幅を広げます。恋愛ソングやバラードで切なさや親密さ、儚さ、ドリーミーな雰囲気を演出したい時によく使われる技法です。
この発声法は聴き手との距離を縮め、より親近感のある歌声を作り出せます。また、通常の発声と組み合わせることで、楽曲にメリハリやコントラストを生み出すこともできます。
ウィスパーボイスは歌だけでなく、さまざまな表現場面で活用されています。 以下のような場面で特にその効果を発揮します。
| 活用場面 | 主な活用例 | 効果・目的 |
| 歌唱 | バラード、アコースティックソング、ラブソングなど | 切なさ、優しさ、繊細さ、親密感の演出 |
| ナレーション | CM、ドキュメンタリー、癒し系ボイスコンテンツ | 耳触りの良さ、リラックスさせる効果、感情の抑揚表現 |
| 朗読 | 絵本の読み聞かせ、ドラマCD、詩の朗読 | 物語世界への没入感、臨場感、温かみの表現 |
このようにウィスパーボイスは表現者の個性を引き立てる重要な発声技術として、多くのプロフェッショナルに活用されています。
ウィスパーボイスを美しく発声するには、余計な力を抜いて自然体で声を出すことが大切です。肩や首に力が入ると、息や声のコントロールが難しくなり、喉を痛めてしまいます。
まず深呼吸をして気持ちを落ち着け、肩を上下に3回動かしたり、首をゆっくり回したりして体の緊張をほぐしましょう。鏡を見ながら自然な姿勢と表情を心がけることも効果的です。
歌やナレーションの前には、発声に関わる筋肉をほぐすストレッチが大切です。ウィスパーボイスの練習前におすすめのストレッチとその効果をご紹介します。
| ストレッチ・ウォームアップ方法 | 具体的なやり方 | 効果 |
| 肩回し | 肩を大きく回す(前後それぞれ10回) | 肩こり解消・上半身の緊張緩和 |
| 首ストレッチ | 首を左右・前後にゆっくり倒す | 喉まわりのリラックス・響きやすい声づくり |
| リップロール | 唇を軽く閉じて「ブルルル…」と震わせる | 息と声のバランス向上・滑舌アップ |
| 舌ストレッチ | 舌を前後左右に出して伸ばす | 発音明瞭・口周りの柔軟性アップ |
| 深呼吸 | ゆっくり5秒吸って7秒かけて吐く | 心身リラックス・呼吸筋のウォームアップ |
これらのストレッチやリップロールは、わずか5分程度でも全身と声帯を効率的にほぐしてくれます。本格練習の前に必ず取り入れましょう。
綺麗なウィスパーボイスを出すには、正しい姿勢と腹式呼吸が基本です。姿勢が悪いと声や息が詰まりがちになり、良い響きやコントロールができません。胸式呼吸では息のコントロールも乱れやすいため、腹式呼吸をしっかり身につけましょう。
正しい姿勢のポイントは以下の通りです。
腹式呼吸は、お腹がふくらむ感覚で息を吸い、お腹を引き締めながらゆっくり吐くのが基本です。簡単な練習で腹式呼吸を身につけましょう。
腹式呼吸はウィスパーボイスだけでなく、すべての発声トレーニングの基礎となります。練習ごとに意識して身につけていきましょう。
ウィスパーボイスを美しく響かせるには、声帯をわずかに閉じた状態で息を流し、最小限の振動を与えることが大切です。一般的な囁き声とは違い、音としてしっかり聞こえるのが特徴です。
まず手のひらを口元に当てて、息が強く当たりすぎないようコントロールしてください。息の流れを意識しながら「はぁ」とやさしく発音し、地声よりも柔らかなトーンで練習します。喉が痛くなったり乾燥したりしないよう注意しましょう。
| 発声方法 | 声帯の状態 | 息の流し方 | 声質 |
| 通常の地声 | しっかり閉じて振動 | moderate | はっきりした音色 |
| ウィスパーボイス | わずかに閉じて弱めの振動 | 柔らかく、やや多め | 空気感を含むやわらかさ |
ウィスパーボイスを「細く弱い声」と思いがちですが、胸や口の中の共鳴を意識すれば奥行きのある響きを作れます。
まず低めの音域で「うー」と長く伸ばしながら、胸に手を当てて振動を感じてください。振動が伝わったら、そこにウィスパー成分をのせていきます。口をやや縦に開き、舌をリラックスさせることで、声を前に押し出しすぎず自然な響きを保てます。響きを感じながら息を足していくのが、ウィスパーボイス特有の空気感を作るコツです。
| やり方 | 効果 | ポイント |
| 低音「うー」で胸への手当て | 共鳴や振動を体感 | リラックスした状態を維持 |
| 発音せずに息で胸共鳴を確認 | 響きの方向性の習得 | 息を吸いすぎない |
ウィスパーボイスは「息」と「声」のバランス調整が重要です。息だけが強すぎると「ただの囁き」になり、逆に声が前に出すぎるとウィスパーらしさがなくなります。
ゆっくり「ささやき声」のつもりで「は・ひ・ふ・へ・ほ」と発音し、息と声のバランスが保てているかをチェックしましょう。自分の声を録音して聞き返すのも上達の近道です。
息の量をコントロールしながら音程を少しずつ変化させる練習も効果的です。最初は息の量が多くても構いません。段階的に声の配分を増やしながら、心地よく響くポイントを見つけましょう。
| 項目 | 観察ポイント | セルフチェックの方法 |
| 息の流れ | 強すぎず弱すぎないか | 手のひらで息のあたり方を確認 |
| 声の成分 | しっかり乗っているか | 録音して聞き比べ |
| 音の透明感 | 空気感が心地よいか | 第三者に聞いてもらう |
松陰高等学校町田校では、体験イベントや学校見学を開催しています。
記事に関するお問い合わせは以下までご連絡ください。
Tel : 042-816-3061(平日9:00-18:00)
ウィスパーボイスを身につけるには、段階的な練習が大切です。レベルに応じた練習を積み重ねることで、美しいウィスパーボイスを習得できます。
まずは喉をリラックスさせ、「はー」と息を吐く練習からスタートします。このとき、声帯を閉じず、声ではなく息だけを通すイメージを持つことがポイントです。
次に、軽く小さな声でささやくように、「おはよう」「ありがとう」などの短いフレーズを繰り返し発音します。余計な力が入っていないか、喉が痛くなっていないかも確認しましょう。
| 練習ステップ | 具体的な内容 | ポイント |
| 1 | 「はー」と息を吐く | 声帯に力を入れずにリラックス |
| 2 | ささやき声で短い言葉を発音 | 音量を抑え、声と息の境界を感じる |
初級で身につけた息の流し方をベースに、今度は音程をつけて歌う練習に進みます。童謡やシンプルなメロディーを、ウィスパーボイスで実際に歌ってみましょう。息が多すぎて声がかすれたり、逆に声が強くなりすぎて「普通の声」にならないよう注意してください。
録音して自分の声を確認し、息と声のバランス・音程の安定感・言葉の明瞭さに注目して何度も練習しましょう。
| 練習フレーズ | 目的 | 注意点 |
| ドレミファソ | 音程を保ったウィスパーボイスの確認 | 音が不安定にならないようにする |
| 短い歌詞(例:チューリップの歌など) | 言葉を乗せてささやく感覚の習得 | 発音がこもらないように意識 |
上級者は、楽曲やフレーズに合わせて息と声の比率を自在にコントロールできるように練習します。同じフレーズでも「息2:声8」「息5:声5」など、度合いを変えながら表現を研究しましょう。
また、楽曲の中でウィスパーボイスと通常の発声を切り替える練習も取り入れて、表現力の幅を広げます。バラード曲や表現力の要求されるフレーズにチャレンジし、録音や実際のパフォーマンスで実践しましょう。
| 練習内容 | 習得ポイント | 具体的練習法 |
| 息と声の配分操作 | 場面に応じた使い分け | 同じ言葉・メロディを「息多め」「声多め」で繰り返す |
| ウィスパーボイスと通常声の切り替え | 歌全体の表現力アップ | サビやAメロごとに切り替えながら歌う |
| 難易度の高い楽曲に挑戦 | 実践力・持久力の向上 | 宇多田ヒカルやAimerなど表現豊かな曲を選ぶ |
これらの練習を着実に積み重ねることで、ウィスパーボイスの表現技術が確実に向上します。自分の声や表現の幅の変化を楽しみながら、定期的な録音・フィードバックを活用してさらなるレベルアップを目指してください。
ウィスパーボイスは、ただ息を多く混ぜて発声する方法と混同されがちですが、「息と声のバランス」が何より重要です。息だけを多く使いすぎると、「息漏れ声」や「ささやき声」になり、本来のニュアンスや響きが失われてしまいます。
声帯が適度に閉じていない場合に起こりやすいため、声帯の振動を感じながら、空気の流れと声質の均衡を意識して発声練習することが大切です。録音して聞き返したり、発声トレーナーの指導を受けるのも有効です。
ウィスパーボイスは息の割合が多いため、発音が不明瞭になりがちです。特に日本語は母音が多く、響きがぼやけやすいため、モゴモゴした印象になってしまうことがよくあります。
口の形や舌の位置を意識し、子音をやや強調するイメージで発音すると、クリアなウィスパーボイスを実現しやすくなります。初心者は鏡の前で表情筋の動きや口の開き具合をチェックする習慣をつけるのがおすすめです。
ウィスパーボイスは息を多く使うため、喉や声帯に負担をかけやすい発声方法です。特に以下のような失敗をしやすいため注意してください。
| 失敗例 | 症状 | 対策・改善策 |
| 声帯を閉じすぎる | 声が出にくくなり、喉に力が入り痛みやすい | 軽く閉じる意識を持ち、喉に余計な力を入れない |
| 息だけで歌う | 声がかすれて声量も落ち、喉の乾きやすさを感じる | 声帯を適度に振動させ「息+声」のバランス発声を心掛ける |
| 無理な高音・低音にチャレンジ | 急激な発声で声帯を消耗・痛める | 自分の音域に合った範囲で徐々に練習を進める |
| 長時間連続して練習 | 喉の疲労や炎症に繋がる | 30分ごとに休憩を入れ、水分補給・ストレッチを徹底する |
喉を守るためには、練習前後のウォーミングアップ・クールダウンや定期的な水分補給も大切です。また、体調が悪いときや違和感があるときは、無理せず練習を中断しましょう。
ウィスパーボイスは、深みのある低音域に息の成分を加えることで、包容力や落ち着き、優しさといった印象を与えることができます。本来持つ声の厚みを生かしつつ、声帯を強く閉じすぎないように緩めることで心地よいウィスパートーンを作り出します。
具体的な練習法としては、「フゥー」という息が多めの発声をベースに、少しずつ声を乗せていくイメージが効果的です。また、声がこもったり、ガサガサになりやすいので、無理に低すぎる声を出さず、声帯に負担をかけないミドル〜ロー域を狙いましょう。
| チェックポイント | ポイント | おすすめアプローチ |
| 息の使い方 | たっぷりと息を流しながら発声 | 腹から息を送り、息漏れしすぎない制御 |
| 声の高さ | ミドル〜ロー域に設定 | 無理な低音より、心地よい自然な高さを意識 |
| 共鳴ポイント | 胸や喉の奥で響かせる | 姿勢を正し胸を開く |
ウィスパーボイスは、明るく透明感のある高音域で柔らかく息を交え、幻想的で繊細な雰囲気や、可憐さ・ミステリアスさを表現できます。特に裏声(ファルセット)と地声を使い分け、声帯の閉じ具合を微調整して繊細なコントロールを行うことで、多彩なバリエーションを生み出せます。
練習ポイントは、「ハァー」や「フゥー」といった息に乗せて少しだけ声を混ぜることを意識し、響きを前に出しすぎず、口の奥や鼻腔あたりに集めていくことで声が拡散せずクリアさを保てます。
| チェックポイント | ポイント | おすすめアプローチ |
| 息の使い方 | 軽やかに長く息を使う | 強く吹かず、吐息交じりの発声 |
| 声の高さ | ミドル〜高音域に設定 | 無理に高くせず、自然な高さで |
| 共鳴ポイント | 鼻腔や口腔内で響かせる | 口の奥で響かせるイメージ |
ウィスパーボイスは、多くの歌手が表現力豊かに活用している技法です。正しい練習法と継続への意識を持てば、誰でも歌唱の幅が広がります。自身の声質を理解し、無理のないトレーニングを積み重ねることで、より深い感情表現と聴く人の心に響くパフォーマンスが可能になります。
※本記事はあくまで一般的な情報提供を目的としております。一部情報については更新性や正確性の保証が難しいため、最新の制度や要件については改めてご自身で各公式機関にご確認ください。
オープンスクールへの参加や、学校案内書の請求はフォームからお申し込みください。
また、学校についてのご相談などはLINEからお問い合わせください。
担当スタッフより迅速にご返答させていただきます。
記事に関するお問い合わせは以下までご連絡ください。
Tel : 042-816-3061(平日9:00-18:00)
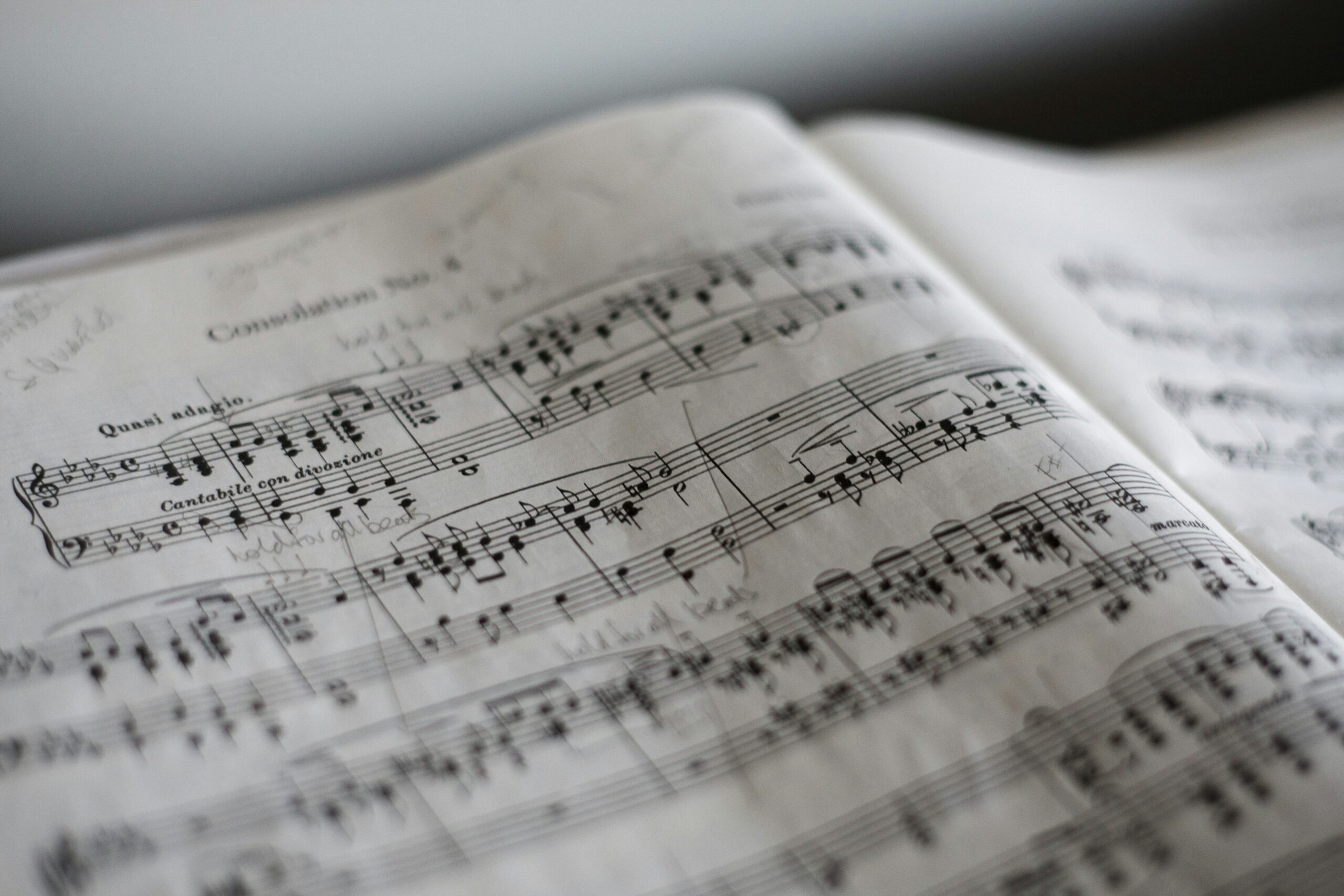
音域 広げる方法完全版!独学ボイトレ・割り箸・筋トレ・裏声... 音域 広げる方法完全版!独学ボイトレ・割り箸・筋トレ・裏声・高音トレー...
2025.08.04

ボイスサンプル 作り方完全版|スマホ録音からセリフ選びまで... ボイスサンプル 作り方完全版|スマホ録音からセリフ選びまで徹底解説
2025.08.16

声優とは?仕事内容から資格・やりがいまで完全ガイド | ア... 声優とは?仕事内容から資格・やりがいまで完全ガイド | アニメから吹き...
2025.07.28

【2025年最新】声優オーディション一般公募情報|未経験か... 【2025年最新】声優オーディション一般公募情報|未経験からアニメ声優...
2025.08.01

リップ音とは?声優が知るべき原因と対処法|出し方のコツも詳... リップ音とは?声優が知るべき原因と対処法|出し方のコツも詳しく解説
2025.08.01

音域チェック完全ガイド|男性・女性の音域一覧と広げる方法【... 音域チェック完全ガイド|男性・女性の音域一覧と広げる方法【どこからすご...
2025.07.31

滑舌を良くする方法|すぐできるトレーニングと早口言葉で劇的... 滑舌を良くする方法|すぐできるトレーニングと早口言葉で劇的改善【子供か...
2025.07.28

絵が上手くなる方法15選!初心者から中学生まで簡単にできる... 絵が上手くなる方法15選!初心者から中学生まで簡単にできる練習法とアプ...
2025.07.31

インフルエンサーとは?仕事内容と収入をわかりやすく解説|日... インフルエンサーとは?仕事内容と収入をわかりやすく解説|日本人有名人の...
2025.07.28

裏声とは?出し方がわからない男性・女性・中学生必見|簡単に... 裏声とは?出し方がわからない男性・女性・中学生必見|簡単にできるコツと...
2025.07.31