
「声が小さい」とお悩みのあなたへ。本記事では、なぜ声が小さくなるのかという原因から、今日から実践できる改善方法、腹式呼吸や発声トレーニング・メンタルケアなど具体的な対策、そして声の悩みを克服するためのステップをわかりやすく解説します。
松陰高等学校町田校では、体験イベントや学校見学を開催しています。
記事に関するお問い合わせは以下までご連絡ください。
Tel : 042-816-3061(平日9:00-18:00)
声が小さいと、相手に自分の話がうまく伝わらず、会話が途切れがちになったり、何度も聞き返されることで会話のテンポが悪くなるというデメリットがあります。特に職場や学校、家族との日常的なやり取りの中で、意図した内容が正確に伝わらないことが増え、結果的に誤解やすれ違いの原因にもなるでしょう。また、相手が聞き取りにくいと感じていることに気を遣いすぎてしまい、会話自体を避けてしまうことも少なくありません。
職場や学校では、声が小さいことが評価や成果に直接結びつく場面も多く、積極的な意見表明やプレゼンテーション、発表などで損をしやすいのが現実です。「発言が聞き取れない」「存在感が薄い」といった印象を与えてしまい、リーダーシップや協調性を正当に評価されにくい傾向があるでしょう。また、グループワークや会議など協働が求められる環境では、他者とのコミュニケーションの取りづらさによって、役割が限定されてしまうこともあります。
| 場面 | 具体的なデメリット | 発生しやすい損失 |
| 会議・プレゼン | 発言が聞き取れず意見が伝わらない | 評価・昇進の機会損失 |
| 授業・発表 | 先生や仲間に伝わりにくい | 成績・信頼の低下 |
| 面接・営業 | 自信がないと判断される | 採用・契約の機会損失 |
声が小さいことで人から何度も聞き返されたり、輪の中で発言がかき消されたりすると、「自分はコミュニケーションが苦手」「自分の意見に価値がない」と感じやすくなり、自己肯定感が下がる傾向があります。その結果、ますます自信を持って発言することが難しくなり、負のループに陥りやすくなるでしょう。こうしたメンタル面での影響は、対人関係を消極的にし、社会的な孤立感やストレスを強めてしまうこともあります。
「もう一度言って」「ごめん、よく聞こえなかった」と言われることが日常茶飯事です。スーパーのレジやコンビニ、職場のちょっとした会話でも、こちらが伝えた内容が相手に届いていないことが多く、繰り返し説明を求められてしまいます。そのたびに「あ、自分の声が小さかったんだ」と気付き、申し訳なさや恥ずかしさを感じる瞬間が多いのが特徴でしょう。
さらに、集団での会話では声が埋もれてしまいがちで、話題の中心から外れてしまうこともしばしばです。自分の発言がちゃんと届いているか常に不安になり、話すこと自体をためらってしまうこともあります。
電話やオンライン会議では、「もう少し大きな声でお願いします」と何度も言われてしまうことがよくあります。直接顔を合わせていない分、繊細な声のニュアンスや口元が読み取れず、普段よりも伝わりにくさを痛感するでしょう。
職場や学校での大事な打ち合わせやグループワークで発言する時も、声が小さいと相手に意図が伝わらず、自分の意見が取り上げてもらえなかった経験も多いです。また、背景雑音に埋もれてさらに聞き取りにくくなるため、話すたびに緊張やストレスを感じてしまいます。
プライベートの場でも「声が小さい」は大きな悩みとなります。カラオケで周囲と比べて声量が出ず、歌声がスピーカーに負けてしまうのが恥ずかしい、という体験談は非常に多いでしょう。
また、騒がしい場所では自分の声が通りにくく、隣の席の人とさえ会話が成立しないこともしばしばです。そのため、話が盛り上がっても自分だけ会話に入りにくかったり、聞き役に徹するしかなくなる人も多いです。
ビジネスシーンや学校行事での発表やプレゼンテーションの際、自分だけが「もっと大きな声で」と注意される、声が小さすぎて後ろの席に聞こえなかったと言われる経験を持つ人は多いでしょう。どんなに内容をしっかり準備していても、伝わらなければ評価されないという悔しさを何度も味わっています。
マイクを使っても緊張して声が震えたり、張り上げることができずに終始控えめな声のまま進行してしまったりすることが多く、自信を無くしてしまうきっかけにもなっています。
| シーン | 「声が小さい」人によくある体験 | 感じやすい感情・悩み |
| 日常会話 | 聞き返される、話が伝わらない | 申し訳なさ、恥ずかしさ |
| 電話・オンライン | 「大きな声で」とよく注意される | ストレス、不安、焦り |
| カラオケ・飲み会 | 盛り上がりに入りづらい、話が通じない | 孤独感、疎外感 |
| プレゼン・発表 | 聞こえないとフィードバックを受ける | 自信喪失、悔しさ |
「声が小さい」という悩みを根本から解決するためには、その原因を正しく理解することが重要です。声量が十分に出ない背景には、単なる個性や体質だけでなく、多様な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、主に「物理的要因」、「生理的要因」、「心理的要因」、「環境的要因」の4つの側面から、声が小さくなりやすい原因を詳しく分析していきましょう。
| 要因 | 具体的な内容 | 該当しやすい例 |
| 物理的要因 | 姿勢悪化や適切な呼吸法ができていないことが影響 | 猫背で話す、肩こりが強い、座り姿勢の崩れなど |
| 生理的要因 | 喉や声帯の健康状態や口周りの筋力不足などが関係 | のどの違和感、声枯れやすい、顎の筋肉の発達不足 |
| 心理的要因 | 自信のなさや緊張、不安などのメンタル面での影響 | 人前で発言するのが苦手、自己主張が苦手 |
| 環境的要因 | 過去の体験や人間関係のトラウマ、育った環境 | 親や教師に声を抑えるよう注意された経験 |
姿勢が悪かったり、身体の力みや緊張から正しい呼吸ができていない場合、声の通り道が塞がれてしまい声が伸びにくくなります。特に現代社会ではスマホやパソコン作業が多く、猫背や前傾姿勢になりがちです。このような姿勢だと胸が圧迫され、深い呼吸がしにくくなり、自然と声が小さくなるでしょう。また、話す時に無意識に息を止めがちな人ほど腹式呼吸が使えず、力強い声になりにくいのです。
声帯や喉の粘膜が常に乾燥していたり、炎症を起こしている場合、声の出力自体が物理的に弱まります。また、口周りや舌の筋力が不足していると、発音がはっきりせず声がこもりがちになり、その結果としても声が小さく聞こえやすくなるでしょう。特に長時間話さない仕事や生活習慣が影響する場合もあり、在宅ワークや独り暮らしで会話量自体が減っている現代人は要注意です。
自分の声に自信が持てない、または失敗経験からくる緊張感が強いと、人は無意識に声を潜めてしまいがちです。人前に立つと緊張や不安が強まる傾向があり、声量が落ちてしまう方も多いでしょう。これは「自己肯定感」の低さとも結びついており、周囲の反応を気にするほど、声が小さくなりやすくなります。
幼児期や学生時代など成長過程で「うるさい」と注意された経験や、発言したときに強い否定を受けた経験があると、発言自体を控える癖が染みついてしまい、大人になっても声を小さくする傾向につながります。また、家庭や学校、職場などの人間関係も影響し、自己主張を控える空気感があると自然と小声が習慣化してしまうでしょう。
このように、「声が小さい」状態の背後には多角的な原因があります。まずはどの要因が自分に最も当てはまるのかを知ることが、確実な改善のための第一歩になります。
腹式呼吸は、声量を高めるうえで最も重要な呼吸法とされています。日本人は日常生活で無意識のうちに胸式呼吸になりがちな傾向がありますが、これは息の量が少なく、声が小さくなりやすい原因でしょう。腹式呼吸では横隔膜を下げてお腹を膨らませるように息を吸うため、身体全体でしっかりと空気を支えることができ、響きのある大きな声を発しやすくなります。
| 呼吸法の種類 | 特徴 | 声への影響 |
| 腹式呼吸 | お腹を膨らませて横隔膜を使いながら息を吸う | 安定した大きな声が出やすく、長く発声できる |
| 胸式呼吸 | 胸を膨らませる形で呼吸する | 浅く短い呼吸となり、声量が不足しがち |
発声の基礎力を養うには腹式呼吸の習得が不可欠であり、声が小さいと悩む方はまずこれを身につけることが近道です。
腹式呼吸の正しいやり方を身につけることが、声量改善の第一歩です。以下の方法で練習を行いましょう。
毎日の継続がコツです。最初はうまくできなくても、必ず変化が現れます。
腹式呼吸を活用した発声トレーニングを併用することで、より効率的に声量をアップさせることができます。
| トレーニング名 | 方法 | 期待できる効果 |
| ロングブレス | 腹式呼吸で息を吸い込み、できるだけ長く一定の「スー」という音を出しながら息を吐く | 息のコントロール力と持久力向上、長く安定した発声に効果的 |
| ハミング発声 | 口を閉じたまま「んー」と腹式呼吸で声を響かせる | 口腔内や鼻腔への響き強化、声の通りを良くする |
| 母音発声 | 腹式呼吸で十分に息を吸い、「あ・い・う・え・お」を大きな声で順番に発声 | 明瞭な発音・声量アップ、口周りの筋力強化 |
いずれの練習も毎日短時間でも実践することで、効果を実感しやすくなります。録音して効果を記録するとモチベーションも維持しやすくなります。
せっかく身につけた腹式呼吸も、日常の中で意識しなければすぐに元の呼吸法に戻ってしまいがちです。無理なく生活に取り入れるためのポイントを紹介します。
「腹式呼吸=特別なトレーニング」ではなく、「毎日の習慣」として体に覚えさせることが大切です。
声が小さいことで悩む方にとって、正しい発声トレーニングは、声量だけでなく「質」や「響き」を改善するためにも有効です。効果的な発声トレーニングを継続的に行うことで、通る声・明瞭な声・疲れにくい声が自然と身につくでしょう。ここでは具体的なトレーニング方法や声の響きを高めるポイントを解説します。
まず重要なのは、声帯を傷めないためのウォーミングアップと、正しい発声の基礎を身につけることです。ウォーミングアップでは、リップロール(唇を震わせながら息を吐く)やハミング(鼻に響かせて声を出す)を取り入れることで、声帯の緊張をほぐし滑らかにするでしょう。
| ウォーミングアップ方法 | 具体的な手順 | ポイント |
| リップロール | 唇を軽く閉じて「ぶるる」と震わせる | 力を抜いて自然な息で行う |
| ハミング | 「んー」と鼻に響かせるように声を出す | 喉を締めずにリラックスして行う |
これらの練習を毎日2~3分取り入れることで、声を出すための土台が整います。
発声の基礎力を向上させるには、「舌」や「口周り」の筋肉を鍛えることも有効です。筋力が不足していると、発音が不明瞭になったり、声がこもる原因にもなるでしょう。代表的なトレーニングには次のようなものがあります。
これらのトレーニングを毎日数回繰り返すことで、滑舌や響きの良い声に近づきます。
声が小さい人は「何を言っているのか分からない」と指摘されがちです。滑舌を良くすることで、聞き取りやすく明瞭な声になるでしょう。おすすめの練習は早口言葉や、母音法(あ・い・う・え・おを強調して発音)です。
| トレーニング方法 | 具体例 | ポイント |
| 早口言葉 | 生麦生米生卵、赤巻紙青巻紙黄巻紙など | ゆっくり正確にを意識。慣れたらスピードアップ |
| 母音法 | 「あ」「い」「う」「え」「お」を意識して発声 | 口をしっかり開けて各母音を明確に出す |
これらのトレーニングは通勤・通学の隙間時間にも行えるので、日常的に取り組むことをおすすめします。
声がこもりやすい人や声量を増やしたい人は、「喉を開く」意識を持つことが重要です。「あくび」の動きをイメージしながら発声することで、喉元に余計な力が入らず、声が響きやすくなります。
こうすることで、声が遠くまで届き、聞き取りやすく、相手に好印象を与える声を作ることができます。日々少しずつ練習を重ねて、自然に喉を開く習慣を身につけましょう。
松陰高等学校町田校では、体験イベントや学校見学を開催しています。
記事に関するお問い合わせは以下までご連絡ください。
Tel : 042-816-3061(平日9:00-18:00)
声が小さいことで悩んでいる方の多くは、「自分の声なんて聞かれたくない」「どうせ伝わらないかも」といったネガティブな自己評価や思い込みを持ちがちです。まずはこうした思い込みに気づき、小さな成功体験を積み重ねることが大切でしょう。例えば、毎日1つ「昨日より少し大きな声であいさつできた」など、実感しやすい目標を記録してください。継続することで自己肯定感が高まり、自分らしく声を発する勇気が育っていきます。
| 課題 | 具体的な改善方法 | 期待できる効果 |
| 自己否定の意識 | ポジティブな自己評価の言葉を毎日ノートに書く | 前向きな自己イメージが作れる |
| 声を出すことへの躊躇 | あいさつや簡単な会話から「少しだけ声量を意識」して話す | 緊張感の軽減、小さな成功体験 |
| 他人と比べてしまう癖 | 「自分なりの成長」を週ごとに振り返る | 自分軸で努力を評価できる |
人前で話す場面に強い苦手意識を持つ方は、少しずつステップを踏んで経験を積むことが効果的です。例えば鏡の前で独り言を言ってみる→親しい友人と少し大きな声で話す→小規模なグループで発言する、といった流れで段階的に難易度を上げていきましょう。学校や職場では発言のタイミングを決めておく、読書会やスピーチクラブに参加するのも有効でしょう。
毎日・毎週の目標設定と、その達成を記録することで堅実に自信を育てることができます。「慣れ」が心理的な壁を取り除く最大の要素となるため、無理をせず継続が大切です。
声が小さくなる主な原因の一つが緊張やプレッシャーによる身体のこわばりや呼吸の浅さです。心理学的なアプローチとしては、認知行動療法やマインドフルネス、イメージトレーニングなどが有効でしょう。
例えば、話す前に数回ゆっくりと深呼吸する・「私は大丈夫」と自分に声をかける・相手が味方であるとイメージする、といった準備が緊張緩和につながります。不安や動揺を感じた際は、その気持ちをそのまま認めて受け入れることも効果的です。自分の現状を否定せず「今できる範囲で頑張る」意識を持ってください。
声が小さい悩みを持つ人は、過去の「うまく聞こえなかった」「聞き返された」経験がトラウマになっていることも少なくありません。完璧を求めず、とにかくチャレンジしてみる姿勢が壁を乗り越える近道でしょう。
身近な人に「最近、声を大きくしようと意識してるんだ」と宣言したり、失敗した時は「うまくできなくて当然」と割り切って、次の機会にまた挑戦するサイクルを心がけてください。失敗経験も成長のためのステップと捉えることで、少しずつメンタルが鍛えられ、以前より声を出すことへの抵抗が薄れていきます。
また、心理的な壁が深刻な場合や自力で改善が難しい場合は、臨床心理士やカウンセラーなど、専門家に相談するのも良い選択肢です。自分らしい声を取り戻し、堂々とコミュニケーションができる日常を目指してください。
日常の会話で声を大きく出すためには、「はっきり話すこと」と「相手に自分の声を届ける意識」を持つことが不可欠です。例えば、相手の目を見て話すことで自然と声量が上がりやすくなるでしょう。また、語尾までしっかり発音することを心がけると、会話全体がクリアに聞こえやすくなります。会話を始める前に深呼吸をしておくと、呼吸が安定しやすく発声がしやすくなるのでおすすめです。
周囲の雑音がある場合でも、相手に自分の声が届いているか確認しながら声のボリュームを調整しましょう。「自分の声が小さいかもしれない」と感じたときこそ、意識して声を出すことが改善の第一歩になります。
声量を確保し安定した発声を続けるためには、声帯や喉の健康を守る生活習慣がとても重要です。乾燥した環境では声帯が傷つきやすくなるため、加湿器の利用やこまめな水分補給を習慣にしましょう。タバコやアルコール、辛いものの摂取は喉への刺激になりやすいため、控えることをおすすめします。
また、咳払いのしすぎや大声で長時間話し続けることも声帯に負担をかけるでしょう。適度に喉を休める意識をもち、睡眠時間をしっかり確保することで、喉や声のコンディションを維持してください。
スマートフォンやパソコンの録音機能、または発声練習アプリを活用することで、自宅でも簡単に声量アップのトレーニングが行えます。録音した自分の声を確認することで、どのくらいのボリュームで話しているか客観的に把握でき、改善ポイントが見えてくるでしょう。
以下のようなアプリや録音方法を日常生活に取り入れてみてください。
| 活用ツール | 主な機能 | おすすめの使い方 |
| スマホ標準の録音アプリ | 自分の声を録音・再生 | 会話や発声練習を録音し、声量や滑舌をチェック |
| 発声トレーニング専用アプリ | 音程・声量の診断、トレーニング課題の提供 | 毎日課題をこなして発声の癖を改善 |
| オンライン会議アプリ | 他人の評価を確認できる | 会議の録音・録画を活用して自分の話し方を分析 |
録音で自分の声を定期的にチェックし、改善点を明確にすることが、声量アップの近道です。
声量アップを目指す上で最も大切なのは、「継続してトレーニングを行うこと」と「小さな成功体験を積み重ねること」です。毎日のルーティーンに、発声練習や簡単なストレッチを組み込むことで、習慣化しやすくなるでしょう。例えば、朝起きてすぐや就寝前、入浴中など決まったタイミングで発声練習を行うようにしてください。
また、自分の成長に気づけるよう、声量や発声の変化を日記やアプリに記録して「見える化」することもモチベーション維持に効果的です。日常で声量を意識するだけでなく、人と話す機会を増やして経験を積むことも大切になります。
声が小さい悩みを根本から解決したい場合、プロによる専門的なボイストレーニングや、自己学習による効果的な練習法を知ることが重要です。ここでは、実際に高い効果が期待できる指導内容や、市販の教材・スクール活用法、独学とプロ指導それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説しましょう。
ボイストレーナーによるレッスンでは、一人ひとりの声質や課題に応じて個別指導が行われます。特に以下の4つの発声法は、多くのボイストレーニング教室で実践されている定番メニューです。正しい方法で継続して練習することで、声量や響きが劇的に変化するでしょう。
| トレーニング内容 | 目的・効果 | ポイント |
| 腹式呼吸法 | 安定した大きな声を出すための基礎づくり | お腹を意識してゆっくり息を吸う・吐くの反復練習 |
| リップロール | 声帯のウォームアップ・音の響き拡張 | 唇を震わせながら声を出し、リラックスした状態を作る |
| 母音発声トレーニング | 発声の安定化と滑舌強化 | 「あ・い・う・え・お」をしっかり発音し響きを意識 |
| 共鳴発声法 | 声を遠くまで通す力の向上 | 頭・胸・鼻の各部位の共鳴を使い分ける練習 |
これらのトレーニングは一見基本的に感じられますが、プロの指導のもとで適切に行うことで効果が格段に高まります。一人では気付きにくい音の癖・発声の歪みを、専門家がすぐにフィードバックできる点が大きなメリットです。
声量アップやしっかりとした発声習得のためには「独学で実践する方法」と「プロのボイストレーナーから指導を受ける方法」があります。それぞれの特徴を比較し、自分にとって最適な学習法を選びましょう。
| 学習法 | メリット | デメリット |
| 独学 | ・コストが抑えられる
・自分のペースで取り組める ・教材や動画、スマホアプリが充実 |
・自己流になりやすい
・間違った方法に気づかない ・継続のモチベーション維持がやや難しい |
| プロ指導 | ・科学的かつ専門的な指導を受けられる
・短期間で効果が現れやすい ・モチベーションを保ちやすい |
・費用がかかる
・通学・スケジュール調整が必要 ・自分に合う講師を探す手間がある |
本気で改善したい場合は、最初だけでもプロの指導を受け、基礎・コツを掴んだ上で独学を取り入れていくのが最もおすすめでしょう。また、東京都内や都市部を中心に多くのボイストレーニング教室が展開されており、オンラインレッスンの選択肢も増えています。
プロ指導を受ける場合も、独学する場合も、効率的な学習手順を押さえて取り組むことで、声の成長を着実に感じられるようになります。
| ステップ | 内容 | 活用できる教材・ツール |
| 1.正しい腹式呼吸を身につける | 腹式呼吸の感覚と意識の徹底 | 書籍「ボイストレーニングの教科書」、YouTube発声講座 |
| 2.基礎発声練習から段階的に始める | 発声・共鳴・滑舌・響きのウォーミングアップ | スマホアプリ「ボイトレ先生」「みんなの声トレ」 |
| 3.自分の声の録音・フィードバック | 実際に聴き返し客観的に分析 | スマートフォン標準録音アプリ |
| 4.プロのレッスンやオンライン添削を利用 | フォーム/発声の修正、課題の特定 | シアーミュージック、USボーカル教室、オンラインボイトレスクール |
忙しい方や人前に出ることに抵抗がある方には、自宅でも実践できるオンライン教材やスマホアプリの併用が非常におすすめです。無理なく継続することで、少しずつ自分の声や発声への自信も高まるでしょう。
声が小さい悩みを克服するには、正しい腹式呼吸と発声トレーニング、そして継続的な練習が重要です。まずは姿勢と呼吸を意識し、「あえいうえおあお」などの発声練習を日常に取り入れてみてください。
記録や録音機能付きのアプリを活用し、自分の成長を実感することが継続のカギです。大きな変化を望まず少しずつ進歩することで、自信も自然と高まるでしょう。
もし改善が難しい場合は、ボイストレーニング教室や話し方教室など専門家の指導を受けてみてください。プロの技術と客観的なアドバイスが突破口になるでしょう。
※本記事はあくまで一般的な情報提供を目的としております。一部情報については更新性や正確性の保証が難しいため、最新の制度や要件については改めてご自身で各公式機関にご確認ください。
オープンスクールへの参加や、学校案内書の請求はフォームからお申し込みください。
また、学校についてのご相談などはLINEからお問い合わせください。
担当スタッフより迅速にご返答させていただきます。
記事に関するお問い合わせは以下までご連絡ください。
Tel : 042-816-3061(平日9:00-18:00)
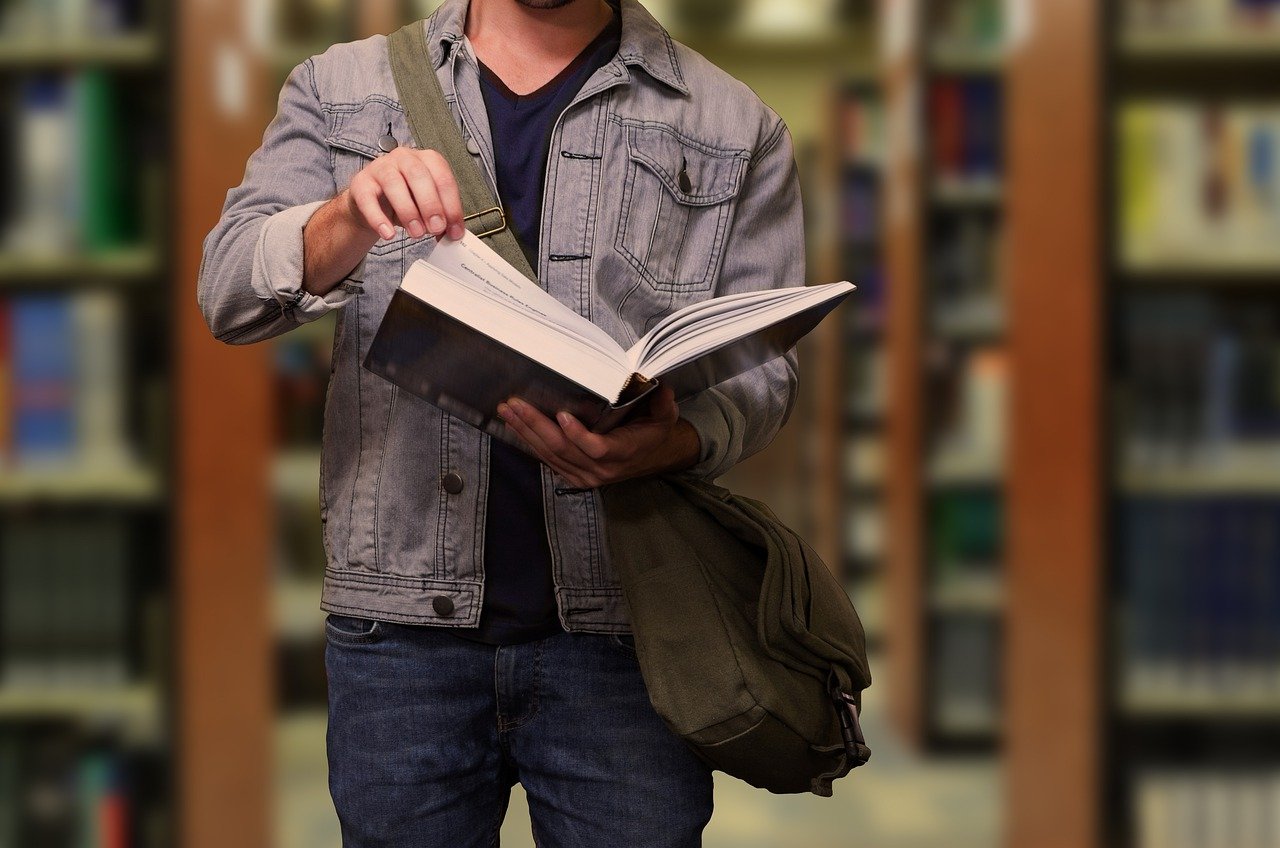
高校生から声優になるには?養成所やオーディション・高校卒業... 高校生から声優になるには?養成所やオーディション・高校卒業後の進路を紹...
2025.08.25

滑舌を良くする方法|すぐできるトレーニングと早口言葉で劇的... 滑舌を良くする方法|すぐできるトレーニングと早口言葉で劇的改善【子供か...
2025.07.28

ファルセットの出し方完全ガイド|男性・女性歌手の違いとミッ... ファルセットの出し方完全ガイド|男性・女性歌手の違いとミックスボイスと...
2025.08.01

絶対音感テストで確認!生まれつき持っている人の特徴・トレー... 絶対音感テストで確認!生まれつき持っている人の特徴・トレーニング方法・...
2025.08.01

相対音感とは?テストとトレーニング方法|絶対音感との違いや... 相対音感とは?テストとトレーニング方法|絶対音感との違いや何人に一人が...
2025.07.31

音域チェック完全ガイド|男性・女性の音域一覧と広げる方法【... 音域チェック完全ガイド|男性・女性の音域一覧と広げる方法【どこからすご...
2025.07.31

滑舌を良くする方法|すぐできるトレーニングと早口言葉で劇的... 滑舌を良くする方法|すぐできるトレーニングと早口言葉で劇的改善【子供か...
2025.07.28

絵が上手くなる方法15選!初心者から中学生まで簡単にできる... 絵が上手くなる方法15選!初心者から中学生まで簡単にできる練習法とアプ...
2025.07.31

インフルエンサーとは?仕事内容と収入をわかりやすく解説|日... インフルエンサーとは?仕事内容と収入をわかりやすく解説|日本人有名人の...
2025.07.28

裏声とは?出し方がわからない男性・女性・中学生必見|簡単に... 裏声とは?出し方がわからない男性・女性・中学生必見|簡単にできるコツと...
2025.07.31