
絵本作家の仕事内容や収入、目指し方について初心者向けに解説します。向いている人の特徴や必要なスキル、主要コンクールの情報も紹介。絵が描けない方でも絵本作家になる方法や、実際の生活事情まで幅広くカバーしています。
松陰高等学校町田校では、体験イベントや学校見学を開催しています。
記事に関するお問い合わせは以下までご連絡ください。
Tel : 042-816-3061(平日9:00-18:00)
絵本作家とは、子ども向けの物語を文章と絵で表現する職業です。文章もイラストも自分で手がける人もいれば、どちらか一方を専門にする人もいます。
童話作家との違いは、絵本作家が文章だけでなく視覚的な表現も重視する点です。絵と文章が組み合わさることで、小さい子どもでも直感的に物語を楽しめるのが絵本の特徴といえるでしょう。
絵本は幼児や小学生向けと思われがちですが、深いメッセージや芸術性から大人にも愛される文化となっています。日本の絵本作家の作品は海外でも評価され、幅広い年代の人が手に取っているのが現状です。
家庭や学校、医療現場でも絵本が活用されており、子どもの読解力や想像力を育てる重要な存在といえるでしょう。
絵本作家の仕事で最も価値があるのは、子どもの心の成長を支えることでしょう。やさしい言葉と印象的な絵で、思いやりや勇気といった大切な気持ちを伝えていきます。読み聞かせをする大人にとっても、新しい発見や感動があるものです。
また、環境問題や多様性といった現代のテーマも、絵本なら子どもにも分かりやすく伝えられます。難しい社会問題を親しみやすい形で表現し、新しい価値観を育む文化的な役割も担っているといえるでしょう。
| 比較点 | 絵本作家 | 童話作家 |
| 作品内容 | 絵と文章で物語を表現 | 物語性の強い文章が中心 |
| 対象年齢 | 乳幼児から大人まで | 小学生~大人 |
| 役割 | 文章と絵の両方orどちらかを担当 | 主に文章のみ担当 |
| 媒体 | 絵本(ビジュアル重視) | 童話(テキスト中心) |
絵本作家の仕事は、アイデア出しから始まって企画書作成、ラフスケッチ、試作本制作、原画制作、最終的な校正まで様々な工程があります。
まずは日常の観察や子どもの発想からテーマを考えます。企画がまとまったら編集者と打ち合わせをして、ラフスケッチを提出するのが一般的です。文章と絵を同時に進めることも多く、試作本を何度も直しながら完成を目指していきます。その後原画を描き、デジタル処理やレイアウト調整を経て印刷所へ。完成までには数ヶ月から1年以上かかることがほとんどでしょう。
| 工程 | 主な内容 | 期間の目安 |
| 企画・構想 | テーマ選定、物語やキャラクターのアイデア出し | 1週間~1カ月 |
| ラフ・ダミー制作 | ラフスケッチ作成、絵と文章の仮配置 | 1カ月~3カ月 |
| 編集・打ち合わせ | 編集者との修正・意見交換 | 随時 |
| 原画制作 | 本番用の絵の作成、デジタル修正作業 | 2カ月~6カ月 |
| 最終校正・入稿 | 誤字脱字、色味などの最終チェックとデータ入稿 | 1週間~1カ月 |
絵本作家にとって、編集者や出版社との連携は欠かせない仕事です。企画段階では、絵と文章のバランスやターゲット層、ページ構成などを話し合います。
校正では、言葉遣いやストーリーの流れ、絵の表現など細かい部分も調整が必要です。出版後は販促イベントやトークショーに参加することもあるでしょう。また、編集者との信頼関係を築くことで、継続的な作品発表や重版につながるため、業界内の人脈作りも大切になります。
絵本作家の仕事は、絵本制作だけではありません。最近では、作品を活かしたグッズ制作やイラスト依頼、ワークショップの講師、読み聞かせ活動など、様々な仕事に広がっています。
| 関連業務 | 具体的な内容 | 効果・メリット |
| イラスト依頼 | 広告や雑誌の挿絵、ポスター、パンフレットへのイラスト提供 | 知名度向上、収入源の多様化 |
| グッズ化展開 | キャラクター雑貨・ぬいぐるみ・文具・カレンダーなどの商品化 | 作品世界の拡散、ロイヤリティ収入 |
| ワークショップ・講演 | 図書館、書店、イベントでの読み聞かせ・ものづくり体験指導 | ファンとの交流、活動の幅拡大 |
| メディア出演 | ラジオ、テレビ、新聞などへの出演・インタビュー対応 | プロモーション、社会的影響力の拡大 |
このように、今の絵本作家は出版以外の分野でも幅広く活動しています。
絵本作家の多くはフリーランスとして活動しています。出版社と直接契約することが多く、時間や場所を自由に選んで働けるのが特徴です。その反面、安定した収入を得るには自己管理や営業力が必要になります。
仕事を得る方法も様々で、原稿の持ち込みやコンテスト応募などがあります。最近は副業から始めて、デビュー後に専業になる作家も多いようです。
絵本作家の収入は、原稿料と印税の2つが主な柱です。原稿料は作品完成時に出版社から一括で支払われます。印税は本の売上に応じてもらえるもので、本体価格の5〜10%程度が相場となっています。
| 収入の種類 | 内容 | 金額目安 |
| 原稿料 | 出版社から依頼された作品に対し、執筆・作画した原稿1冊に対して一括で受け取る報酬 | 約10万円〜30万円(1冊あたり) |
| 印税 | 出版された絵本の売上部数に応じた収入。一般的に本体価格×5〜10% | 例:定価1,000円・10%印税なら1冊売れるごとに100円 |
| その他の収入 | グッズ、関連イベント出演、原画展、読み聞かせ講師など副次的な活動 | イベント1回数万円〜、グッズは契約内容次第 |
新人作家の原稿料は低めになることが多いようです。ベストセラーになれば印税収入が大きくなりますが、売れなければ印税はほとんど期待できません。そのため、安定した収入を得るには複数の作品を手がけたり、関連する仕事も並行して行う必要があるでしょう。
絵本作家の年収は、作品の売れ行きによって大きく差があります。専業でやっている作家は一部で、多くの人は他のイラストや執筆、講演、ワークショップなどと兼業して生活しています。年収100万円以下の作家も珍しくありませんが、人気作家になると1,000万円を超えることもあるようです。
| 年収レンジ | 人数の割合 | 特徴 |
| 100万円未満 | 多い | 新人作家や兼業作家など。収入源が複数ある場合も多い |
| 100万円〜300万円 | やや少数 | 複数の作品を商業出版し、副業収入と合わせて生活 |
| 300万円〜1,000万円以上 | かなり稀 | ロングセラーや大型契約、著名な作家 |
絵本作家は夢のある仕事ですが、安定した収入を得るには戦略的な活動と地道な努力が必要です。収入を増やすには、継続的な作品発表に加えて、グッズ化やイベントなど関連ビジネスも大切になってきます。
美術系の学校で学ぶことは、絵本作家を目指す上で大きなメリットとなるでしょう。美術大学、芸術系の専門学校や短大には、絵本コースやイラストコース、デザイン学科などが設置されています。
これらの学校では、デッサンや色彩構成、イラストレーション、物語の構成、製本技術など、絵本制作に必要なスキルを体系的に学ぶことが可能です。在学中から自作絵本の制作や学内コンクール、展示会への参加など、作品発表の機会も豊富にあります。
卒業後は、卒業制作を出版社へ持ち込んだり、コンクールに応募して作家デビューを目指すのが一般的です。プロの絵本作家や現役編集者から直接指導を受けられることも多く、人脈や実践的なアドバイスが得られる点も見逃せません。
出版社への持ち込みは、絵本作家デビューの重要なチャンスです。まず、自分の作品を原画またはダミー本として丁寧にまとめます。ダミー本は完成した絵本と同じ形に仮綴じしたもので、実際にページをめくって物語を確認できるものです。
出版社ごとに持ち込み方法や必要資料が異なるため、公式サイトを必ず確認して指示に従いましょう。編集者が直接作品を見てくれるので、フィードバックをもらえたり、書籍化のきっかけになることもあります。
持ち込みでは自己紹介や企画の狙いを明確にして、創作への熱意を伝えることが大切です。郵送やWeb応募、直接訪問など方法は様々なので、事前の情報収集が欠かせません。
コンクールやコンテストは、絵本作家デビューの定番ルートといえるでしょう。主要出版社が毎年全国規模で開催しています。受賞すれば、書籍化やプロデビュー、著名な編集者や作家との協力といったチャンスが広がります。
コンクール応募では、募集要項(ページ数、テーマ、用紙サイズなど)を必ず守り、自分らしい視点や発想が伝わる作品を作ることが大切です。過去の受賞作を調べて、応募先の傾向を分析するのも効果的でしょう。一次選考後に編集者からアドバイスがもらえるコンクールもあるので、成長の機会として活用できます。
絵本作家として活躍するには、絵や文章の技術だけでなく、独自の視点や創造性、子どもに寄り添う感性といった特別な資質が必要です。どんな人が絵本作家に向いているのか、具体的な特徴を見ていきましょう。
絵本では、ファンタジーの世界や日常の何気ない出来事を独自の視点で切り取り、子どもの心に残る物語や絵を作る力が大切です。発想力や空想力はもちろん、身の回りの小さな変化に気づく観察力や、出来事の本質を理解する洞察力も必要になります。これらが絵本の魅力である「発見」と「驚き」を生み出すのです。
| 資質・能力 | 具体例 | 絵本作家への重要性 |
| 創造力 | 動物が話す世界を想像する、斬新な発明を物語に取り入れる | オリジナリティのある作品作りに必須 |
| 観察力 | 子どもの仕草や言葉遣い、日常の細やかな違いに気付く | リアリティある登場人物や場面描写の基礎 |
| 洞察力 | 子どもの本音や感情の背景を深く理解する | 共感や気づきを誘う深い物語性の創出 |
絵本は主に子どもが読むものなので、子ども目線で物事を考え、子どもの好奇心や疑問、喜びや不安に寄り添う感性が大切です。大人では思いつかない視点や表現が、子どもの共感を呼んで絵本の魅力を高めます。
例えば、擬音語や繰り返し表現など、子どもが楽しめる言葉選びや、子どもが主人公になりやすいストーリー構成を考える力も必要でしょう。常に読者の子どもたちの体験を想像して、物語に活かせることが重要といえます。
絵本作家は一人で作品を作るのではなく、編集者やイラストレーター、出版社の担当者、時には読者の子どもや保護者と意見を交わすことが多いため、コミュニケーション能力やプレゼン力も大切になります。
作品の意図やコンセプトを的確に伝えたり、打ち合わせで受けたアドバイスを柔軟に受け止める姿勢が必要です。読み聞かせイベントやワークショップで子どもたちと直接関わる機会もあるので、自分の言葉で作品の魅力を伝える力も重要でしょう。
| 能力 | 関連する場面 | 求められる理由 |
| コミュニケーション能力 | 編集者・イラストレーターとの打ち合わせ、共同制作 | 円滑な作品づくり・意図の共有 |
| プレゼン力 | 出版社への企画提案、読み聞かせイベント | 作品の魅力を効果的に伝える |
絵本作家には、表現技術だけでなく、人の気持ちを想像して共感する力や、いろんな角度から物事を見る柔軟さも大切です。こうした力を普段から意識して伸ばしていけば、絵本作家への道が開けてくるはずです。
松陰高等学校町田校では、体験イベントや学校見学を開催しています。
記事に関するお問い合わせは以下までご連絡ください。
Tel : 042-816-3061(平日9:00-18:00)
絵本作家になるには、絵が上手い・文章が書けるだけでは足りません。いろんなスキルや表現技術が必要になってきます。現役の絵本作家や編集者が重視している代表的なスキルを見ていきましょう。
絵本はページをめくるたびに物語が展開されるので、作画力がとても重要です。キャラクターの表情や動き、色遣いや構図を通して、物語の雰囲気や登場人物の気持ちを自然に伝える画力が必要になります。
特に大切なのが、「この作家ならでは」と読者が感じる独自性や作風でしょう。流行のテーマに頼るだけでなく、自分らしいオリジナリティや独特のタッチが作品の人気を左右します。林明子さんやいわむらかずおさんなど、作家ごとに個性豊かな絵本が愛され続けているのもそのためです。
絵本は短いページ数の中に、簡潔でありながら深みのある物語を作る必要があります。物語の起承転結や、子どもの心をひきつけるリズムや繰り返し、心に残るラストなど、すべてが計算されていないといけません。
また、年齢に合わせて分かりやすく親しみやすい言葉を選ぶ力も大切です。豊富な語彙や表現力と、子どもや親の心に響く物語を作る力を日々磨いていくことが重要でしょう。
| 重要なストーリー技術 | 具体例 |
| リズム感のある文章 | 繰り返しやオノマトペを効果的に使う |
| 年齢層に合った表現 | 3歳向け:短いフレーズ、ふりがな活用
小学生向け:少し難しい語彙も取り入れる |
| 余韻の残る結末 | ハッピーエンドだけでなく考えさせる終わり方 |
最近の絵本制作では、アナログとデジタル両方の技術が必要になってきました。PhotoshopやIllustratorなどのデジタルツールは、下絵制作や彩色、レイアウト調整、出版社とのデータやり取りなど幅広く使われています。
デジタル技術があると、いろんな画風や質感の表現ができて、修正も素早く対応できます。グッズや電子絵本、広告など他の分野にも展開しやすくなるでしょう。出版社の規格や印刷の特性を理解して、デジタルデータできれいに納品できることは大きな強みになります。
| 主なデジタルツール | 主な機能 | 絵本制作での活用例 |
| Photoshop | 画像編集・彩色 | 水彩風・パステル風の表現/色補正/原稿データ作成 |
| Illustrator | ベクター画像編集 | 文字組み/レイアウト/グッズ用イラスト制作 |
アナログ技法の魅力を活かしつつも、デジタルツールとの組み合わせは今後ますます必須スキルとなっていくでしょう。
絵が得意でなくても絵本作家になる道はあります。すべての絵本作家が絵と文章の両方を手がけているわけではありません。文章だけを専門にする絵本作家も多く、絵は別のイラストレーターや画家と分業するのが一般的です。
例えば、多くの有名な絵本作家も文章だけ、あるいは絵だけを担当しています。物語の構成や文章表現、言葉遊びやメッセージなど、独自の世界観を作れることが文章専門の絵本作家には大切です。編集者やイラストレーターとのコミュニケーションも重要になります。
多くの絵本は、文章を書く人とイラストレーターによる分業で作られています。大手出版社の絵本コンクールでは、文章部門と絵部門の両方で募集していることが多く、文章だけで応募することもできます。採用されると、編集者が適切なイラストレーターを選んで、絵と文章を組み合わせた作品作りが始まります。
代表的な絵本制作の分業例をまとめてみました。
| 担当 | 主な役割 | 求められるスキル |
| 文章作家 | 物語の構築、セリフ・文章表現、メッセージ性の創出 | 物語構成力、語彙力、感性、伝える力 |
| イラストレーター | キャラクターデザイン、絵本の画作成、世界観のビジュアル化 | 作画技術、色彩・構図のセンス、表現力 |
| 編集者 | 制作進行管理、両者の調整、出版・販促企画 | 企画力、調整・進行管理能力、マーケティングスキル |
文章と絵をそれぞれの専門家が高いレベルで仕上げることが、最近の絵本界では重視されています。絵が苦手でも文章力や物語性が優れていれば、分業を活かして絵本作家として活躍できるでしょう。
絵が描けなくても、優れたストーリー展開や忘れられないキャラクター、子どもの心に響く言葉など、文章で勝負できる強みがあれば絵本作家になることは十分可能です。自作の物語を出版社に持ち込んだり、文章部門のある絵本コンクールに応募してみましょう。
編集者に認められるには、繰り返し構成や音読しやすさ、親子で読めるテーマなど、絵本ならではの特徴を意識した文章を書くことが大切です。相性の良いイラストレーターや作画パートナーを探して共同制作するのも良い方法でしょう。
文章に自信がある人は、絵本コンテストを活用したり、SNSやブログで自作ストーリーを公開するのもおすすめです。反響を得ることで、出版や商業作品化につなげやすくなります。
絵本作家になるために必要な国家資格や公的資格はありません。ただし、スキルアップに役立つ民間資格や検定はいくつかあり、出版社へのアピールにも使えます。以下の資格・検定は、絵本制作に必要な知識や技術の証明になるので参考にしてください。
| 資格・検定名 | 主な内容 | 得られるスキル・知識 | 運営団体 |
| 色彩検定 | 配色・色彩設計の基礎 | 色の組み合わせ、色彩心理 | 公益社団法人色彩検定協会 |
| 絵本専門士 | 絵本の歴史・選書・読み聞かせ | 絵本の知識、子どもへの読み聞かせ技法 | 東京子ども図書館 |
| イラストレーション技能検定 | イラスト技法・デジタル作画 | 作画スキル、ソフト操作技術 | 一般社団法人日本イラストレーター協会 |
| 日本語検定 | 語彙・文法・表現力 | 文章表現、ストーリー構築力 | 公益財団法人日本漢字能力検定協会 |
自分が伸ばしたい分野に合わせて資格や検定を組み合わせると、より効果的でしょう。
絵本作家を目指すには、独学で挑戦する方法と、専門学校や大学で体系的に学ぶ方法があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットをまとめてみました。
| 学習方法 | 主な特徴 | メリット | デメリット |
| 独学 | 書籍やネット、ワークショップなどを活用して、自主的に学ぶ。 | 費用が抑えられ、自由な時間に学習可能。
自分のペースでオリジナリティを追求しやすい。 |
フィードバックや情報収集が難しい。
業界ネットワーク作りや卒業制作発表の機会が少ない。 |
| 専門学校・大学 | 美術大学、短期大学、デザイン系専門学校で指導を受ける。 | 体系的な知識・技術を習得可能。
現役作家や編集者から直接指導を受ける機会が多く、人脈形成にもつながる。 |
学費や時間的コストがかかる。
カリキュラムが固定的な場合がある。 |
自分のライフスタイルや目指す作家像、既存スキルに応じて学習方法を選ぶことが成功への近道です。
出版社への持ち込みやコンクール応募、編集者との打ち合わせには、ポートフォリオ(作品集)が欠かせません。完成度が高いほど、プロとしての実力や個性をアピールでき、デビューにつながりやすくなります。
ポートフォリオ作成のポイントは次の通りです。
質の高いポートフォリオは、出版社やコンクール審査員の印象を大きく左右します。定期的にブラッシュアップし、最新の代表作を加える努力をしましょう。
絵本作家としてデビューした後も、継続的に作品を生み出し、成長し続けることが大切です。デビューで満足せず、新しいテーマや技法にチャレンジしたり、時代のニーズや子どもの興味に合わせた作品作りを心がけましょう。
読者の声に耳を傾け、フィードバックを作品に活かせる柔軟さも重要です。ロングセラーを目指せる普遍的な物語やキャラクターを生み出すことも、絵本作家として安定したキャリアを築く上で欠かせません。
自分の作品をまとめたポートフォリオは定期的に更新して、出版社や編集者にアピールできるようにしておきましょう。いろんなジャンルや画法、物語の幅を意識したラインナップにすると評価が高まります。
コンクールやコンテストに積極的に応募して、受賞歴やメディア掲載実績を積み重ねれば、作家としての信頼度が高まり、より大きなプロジェクトや出版につながるでしょう。
絵本作家として長く活躍するには、出版社や編集者との信頼関係が欠かせません。編集者のアドバイスや意図を理解し、チームでより良い絵本を作る姿勢が、新たなチャンスや次回作につながります。納期や品質などプロ意識を持った仕事ぶりも、信頼される作家として大切な要素です。
| 出版社・編集者との関係で大切なポイント | 具体的な行動例 |
| コミュニケーション | 進捗報告や相談をこまめに行う、意見交換を積極的にする |
| 納期厳守 | スケジュール管理を徹底し、遅延リスクが生じた場合は早めに連絡 |
| 柔軟性 | 編集側の要望に応じて修正や提案を受け入れる姿勢を持つ |
| 信頼構築 | 一貫した品質や誠実な対応を継続 |
絵本作家として長く活躍するには、技術だけでなく、人間としての魅力や独自性を磨き続けることが大切です。市場の動きや読者層の変化に敏感でいることも重要でしょう。
新しい表現手法やデジタル技術の習得、SNSやWebサイトでの情報発信など、発表方法も時代に合わせて更新していきましょう。講演やワークショップ、イベントへの参加でファン層を広げたり、業界内の人脈を作ることもできます。自分の作品世界をいろんな形で展開すれば、絵本作家としてのブランド力が高まり、安定したキャリアにつながるはずです。
| 取組み内容 | 期待できる効果 |
| 創作活動の継続 | 作品数の拡大・多様化、実績の積み上げ |
| 業界イベント・講演への参加 | 業界内のネットワーク拡大、露出の増加による知名度向上 |
| マーケティング・広報活動 | 自作のPR、新規ファン獲得や書籍販売促進 |
| デジタルスキルの習得 | 新たな表現方法の導入や出版形態への対応 |
| 多角的な展開(グッズ化・映像化など) | 収益源の多様化、ブランド力・認知度の強化 |
絵本作家になるには、創造力や観察力、文章・作画力などいろんなスキルが必要ですが、資格は必要なく、独学や専門学校、持ち込みやコンクール応募など様々な道があります。講談社絵本新人賞などを活用して、ポートフォリオを準備しながら一歩ずつ行動していけば、きっと道が開けるでしょう。
※本記事はあくまで一般的な情報提供を目的としております。一部情報については更新性や正確性の保証が難しいため、最新の制度や要件については改めてご自身で各公式機関にご確認ください。
オープンスクールへの参加や、学校案内書の請求はフォームからお申し込みください。
また、学校についてのご相談などはLINEからお問い合わせください。
担当スタッフより迅速にご返答させていただきます。
記事に関するお問い合わせは以下までご連絡ください。
Tel : 042-816-3061(平日9:00-18:00)

絵が上手くなる方法15選!初心者から中学生まで簡単にできる... 絵が上手くなる方法15選!初心者から中学生まで簡単にできる練習法とアプ...
2025.07.31

イラストレーターとは簡単に解説!資格・仕事内容からなり方ま... イラストレーターとは簡単に解説!資格・仕事内容からなり方まで完全ガイド
2025.07.28

イラストレーターになるには何が必要?独学でもいける?仕事内... イラストレーターになるには何が必要?独学でもいける?仕事内容からなり方...
2025.07.28
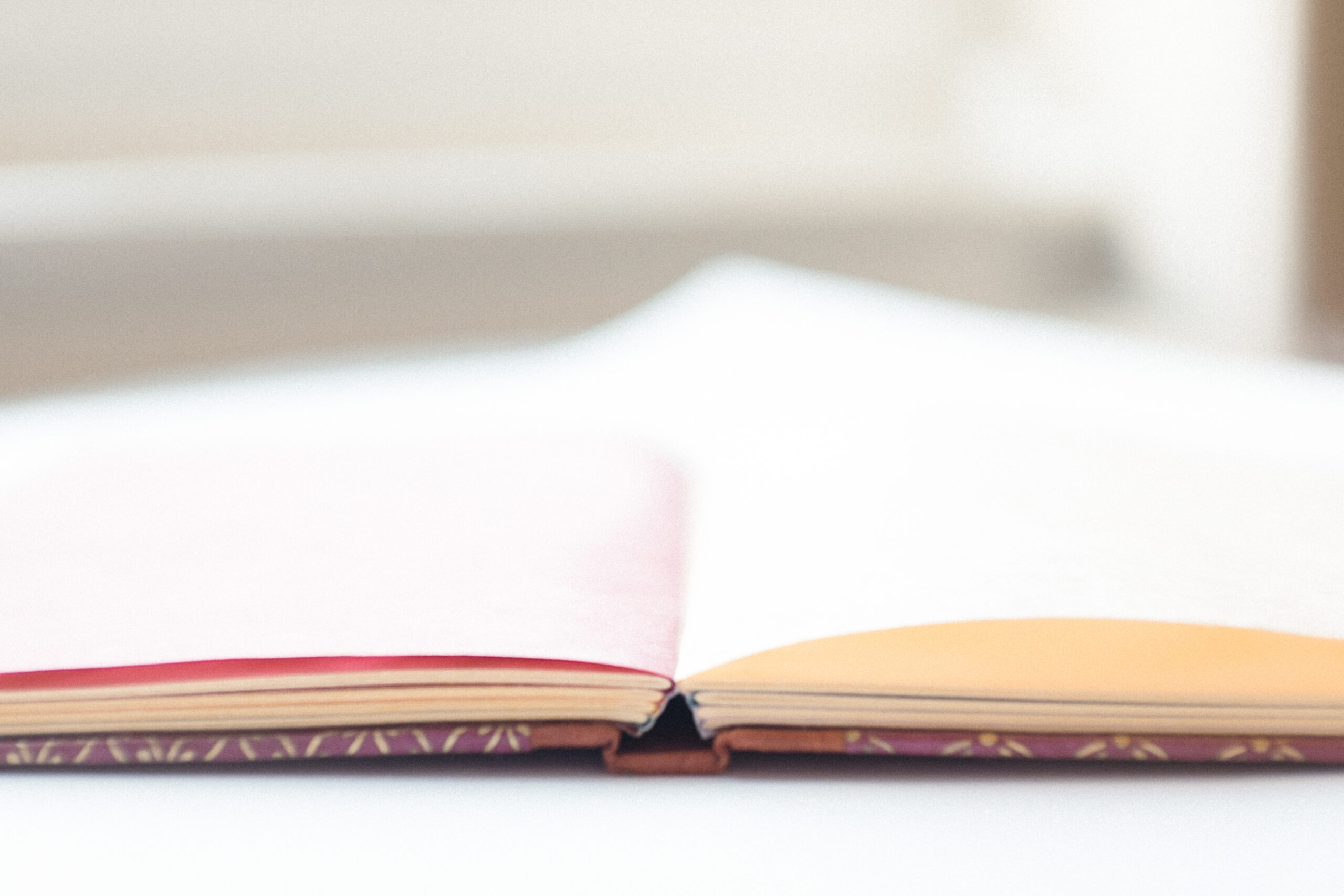
【2025年最新】絵本作家になる成功ロードマップ〜収入・コ... 【2025年最新】絵本作家になる成功ロードマップ〜収入・コンクール・大...
2025.07.31

音域チェック完全ガイド|男性・女性の音域一覧と広げる方法【... 音域チェック完全ガイド|男性・女性の音域一覧と広げる方法【どこからすご...
2025.07.31

滑舌を良くする方法|すぐできるトレーニングと早口言葉で劇的... 滑舌を良くする方法|すぐできるトレーニングと早口言葉で劇的改善【子供か...
2025.07.28

絵が上手くなる方法15選!初心者から中学生まで簡単にできる... 絵が上手くなる方法15選!初心者から中学生まで簡単にできる練習法とアプ...
2025.07.31

インフルエンサーとは?仕事内容と収入をわかりやすく解説|日... インフルエンサーとは?仕事内容と収入をわかりやすく解説|日本人有名人の...
2025.07.28

裏声とは?出し方がわからない男性・女性・中学生必見|簡単に... 裏声とは?出し方がわからない男性・女性・中学生必見|簡単にできるコツと...
2025.07.31